あらためて、公教育を問う
4月27日の日曜日。G・Wの2日目の朝。
気持ちの良い快晴だ。でも寒暖差が大きく朝ウォークは寒かった。
この日記を書くとき、私はパソコンを開いて、そのとき頭に浮かんだことをタイトルにする。
物価も、関税も、ウクライナもあるけど、今朝は仕事がらみの公教育のことだ。
学校の働き方改革が叫ばれて久しい。そしてそれは、ますます悲惨な方向に向かっている。
圧倒的な教師不足問題。国は増員しようとしていない。子どもの数も減っていくからと。
そして教師志望の教育系学生は、どんどん教師になることをあきらめ始めている。
教員採用試験に合格した学生の多くが辞退したという話は、ある県の特別の話ではない。どこでも。
この状況に対しての、国の反応というか対策というのが・・・また悲しい。
給特法(教員給与特別措置法)という50年以上前から変わっていないものを現在検討中だが、その基本姿勢は、教師の時間外の仕事に対して残業手当を支給しないで、わずかな基本給の調整を時間をかけて少しずつ進めるということらしい。
企業の仕事とは質が違い、教師は一人の人間として自らの学びが常に必要な業務だ。
しかしこの10~20年、教師の業務多忙化はすさまじい。デジタル化でさらに。
国は「生身の教師」を減らして、AIに代行させようとでも考えているのではなかろうか?
それは、教育を知らない人の考えることだ。教育の根幹は「生身の人間同士のふれあい」である。
子どもたちは学校で家族以外の人とふれあい、社会というものを認識する。そして「ふれあい」の大切さを。
ここまで一気に書いてしまった。
パソコンを開く前まで、コメの輸入のことが頭に浮かんでいた。とんでもないと。
食糧自給率が38%(世界でほぼ最低ランク)の日本が、コメまで投げ捨てて・・・。この話も悲しい。



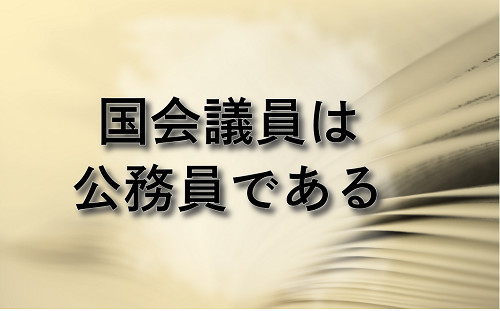
コメント
コメントがありません